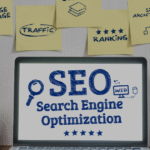BtoBビジネスにおけるリード獲得の手法として、オウンドメディアでのブログ運営が注目されています。
しかし、やみくもに記事を量産しても成果には結びつきません。
BtoBのリード獲得を成功させるためには、ターゲットの課題を的確に捉え、戦略的に記事を作成する技術が必要です。
この記事では、BtoB企業のマーケティング担当者に向けて、リード獲得数を倍増させるための具体的な記事作成のステップや成功のコツを解説します。
なぜBtoBビジネスにおいて記事作成がリード獲得に有効なのか
BtoBビジネスにおいて記事作成が重視される理由は、潜在的な顧客層へ継続的にアプローチできる点にあります。
広告のような即時性は低いものの、顧客の課題解決に役立つ質の高い記事は検索エンジン経由で長期的に見込み客を集め続けます。
これにより、広告費をかけずに自社の認知度を高め、将来の顧客となる層との接点を構築可能です。
また、専門的な情報を提供し続けることで、業界内での専門家としての地位を確立し、顧客からの信頼を獲得できます。
このように、記事は一度作成すれば企業の資産として蓄積され、中長期的なリード獲得の基盤を形成するのです。
まず理解すべきBtoBとBtoCにおける記事作成の決定的な違い
BtoBとBtoCでは、ターゲットとなる顧客の購買行動や意思決定プロセスが大きく異なります。
そのため、リード獲得を目的とした記事作成においても、その違いを明確に理解し、アプローチを変える必要があります。
BtoBは企業対企業の取引であり、BtoCは企業対個人の取引です。
この根本的な違いが、記事で伝えるべきメッセージの内容や表現方法、そして最終的なゴール設定にまで影響を及ぼします。
toBならではの特性を把握することが、成果を出す記事作成の第一歩です。
違い1:検討に関わる人数と期間の長さ
BtoBの購買プロセスは、複数の部署の担当者や決裁者が関与するため、検討期間が数ヶ月から一年以上と長期にわたるのが一般的です。
個人の判断で購買が決まるBtoCとは異なり、組織としての合理的な判断が求められます。
そのため記事作成においては、現場の担当者向けの実務的な情報から、管理職や経営層向けの費用対効果や導入事例といった情報まで、それぞれの立場にいる関係者が必要とする情報を網羅的に提供する視点が求められます。
各検討フェーズで発生する疑問や懸念を解消するコンテンツを用意し、長期的な検討プロセスを支援していく必要があります。
違い2:論理的で合理的な判断基準
BtoCの購買動機が個人の感情や好み、トレンドに左右されやすいのに対し、BtoBの購買決定は企業の課題解決や生産性向上、コスト削減といった極めて論理的かつ合理的な基準に基づいて行われます。
したがって、記事コンテンツも感情に訴えかける表現より、客観的なデータや具体的な数値、詳細な導入事例などを用いて、製品やサービスがもたらすメリットを論理的に説明することが重要です。
製品のスペックや機能が、どのようにして企業の利益に貢献するのかを明確に示し、読者が合理的に導入を判断できるような情報を提供しなければなりません。
違い3:最終ゴールは信頼関係の構築
BtoB商材は高額であったり、長期契約が前提であったりすることが多いため、企業は取引相手を慎重に選びます。
単に製品を売って終わりではなく、導入後も長期的なパートナーとして付き合えるかどうかが重要な選定基準となります。
そのため、記事作成の最終的なゴールは、目先のリード獲得だけではなく、専門的な情報提供を通じて「この分野ならこの企業が一番詳しい」「この企業は信頼できる」という専門家としてのポジションを確立し、顧客との信頼関係を構築することにあります。
継続的な価値提供を通じて、自社を第一想起してもらう状況を作り出すことが求められます。
【7ステップで解説】リード獲得に繋がるBtoB記事の作り方
BtoBでリード獲得という成果を出すためには、思いつきで記事を作成するのではなく、戦略に基づいた体系的なプロセスを踏むことが不可欠です。
ここでは、事業目標の設定から記事公開後の改善まで、具体的な7つのステップに分けて、成果に繋がるBtoB記事の作り方を解説します。
この手順に沿って進めることで、読者のニーズを満たし、かつビジネス目標の達成に貢献する質の高い記事を効率的に作成することが可能になります。
Step1:事業目標から逆算して記事のKPIを設定する
記事作成に着手する前に、まずメディア運営の最終的な事業目標を明確にします。
例えば「年間売上をX%向上させる」という目標があれば、そこから逆算して「そのために必要な商談数」「商談化に必要なリード数」を算出します。
そして、記事が担うべき役割として「月間リード獲得数」や「記事経由の資料請求数」「ホワイトペーパーのダウンロード数」といった具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定します。
KPIを定めることで、作成する記事の方向性が明確になり、公開後の効果測定の基準も定まります。
目的意識を持って施策を進めるために、この最初のステップが極めて重要です。
Step2:ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を具体的に設計する
次に、どのような読者に記事を届けたいのか、具体的な顧客像である「ペルソナ」を設計します。
BtoBの場合、ペルソナには企業の業種や規模、事業内容といった企業情報に加え、担当者の所属部署、役職、業務内容、抱えている課題や悩み、情報収集の方法などを詳細に設定します。
例えば「従業員数100名規模の製造業で、人事部の採用担当者。若手人材の定着率の低さに悩んでおり、解決策を探している」のように具体化します。
ペルソナを明確にすることで、記事のテーマや切り口、専門性のレベル、トーン&マナーが定まり、ターゲットに深く響くコンテンツ作成が可能になります。
Step3:顧客の課題に基づいたSEOキーワードを選定する
設定したペルソナが、自身の課題を解決するためにどのようなキーワードを使ってwebで検索するかを想定し、SEOキーワードを選定します。
例えば、先ほどの人事担当者のペルソナであれば、「新人離職率原因」「若手社員育成方法」といったキーワードが考えられます。
キーワード選定では、検索ボリュームの大きさだけでなく、そのキーワードで検索するユーザーの意図(検索意図)と、自社の製品やサービスで解決できる課題が合致しているかが重要です。
また、競合サイトの状況も調査し、自社が上位表示を狙えるキーワードを見極める戦略的な視点も求められます。
Step4:読者の検索意図を満たす記事構成を作成する
選定したキーワードで検索する読者が、どのような情報を求めているのか(検索意図)を深く分析し、その答えを網羅する記事構成を作成します。
検索結果の上位に表示されている競合記事を参考に、読者が知りたいであろうトピックを洗い出し、見出しとして整理します。
構成案を作成する際は、読者がスムーズに内容を理解できるよう、情報の提示順序を論理的に組み立てることが大切です。
単に情報を羅列するのではなく、読者の疑問に先回りして答えを示し、読み終えたときに課題解決の道筋が見えるようなストーリーを描くことで、満足度の高い記事になります。
Step5:専門性と信頼性を担保した質の高い本文を執筆する
作成した構成案に沿って、本文を執筆します。
BtoBコンテンツでは、情報の正確性、専門性、信頼性が特に重視されます。
公的機関が発表している統計データや調査結果を引用したり、社内の専門家(技術者や営業担当者など)にヒアリングした内容を盛り込んだりすることで、記事の権威性を高めます。
また、専門用語は避けすぎず、必要に応じて使いつつも、誰が読んでも理解できるよう平易な言葉で解説を加える配慮が求められます。
他社の記事にはない独自の知見やノウハウを盛り込むことで、コンテンツの価値をさらに高めることができます。
Step6:見込み客を次の行動へ導くCTAを設置する
記事を読んで課題意識が高まった読者を、次の行動へと促す仕掛けがCTA(CallToAction)です。
記事の末尾や途中に、関連する資料のダウンロードフォーム、セミナーやウェビナーの申込ページ、製品に関する問い合わせフォームへのリンクなどを設置します。
重要なのは、記事の内容と関連性の高いCTAを用意することです。
例えば、「人事評価」に関する記事であれば「人事評価シートのテンプレート」のダウンロードを促すなど、読者が「これも欲しい」と感じる自然な流れを作ります。
適切なCTAを設置することで、記事の閲覧者を具体的な見込み客へと転換することが可能になります。
Step7:記事公開後は数値を分析して改善を繰り返す
記事は公開したら終わりではありません。
公開後は、Googleアナリティクスやサーチコンソールといった分析ツールを用いて、設定したKPIの達成度を定期的に計測します。
具体的には、検索順位、クリック率、ページビュー数、滞在時間、直帰率、そしてコンバージョン率などの数値を確認します。
これらのデータに基づき、記事のパフォーマンスを評価し、課題を特定します。
例えば、検索順位が低い場合はSEO対策の強化、滞在時間が短い場合は内容の改善や構成の見直しといったリライトを行います。
この分析と改善のサイクルを継続的に回すことで、記事の効果を最大化していきます。
記事の効果を最大化させるために意識したい3つのコツ
基本的な作成ステップに加え、いくつかのコツを意識することで、記事の効果をさらに高めることが可能です。
BtoBの記事作成では、単にSEO対策を施すだけでなく、読者であるビジネスパーソンとの信頼関係をいかに構築するかが重要になります。
ここでは、記事の効果を最大化させるために特に意識したい3つのコツを紹介します。
これらを実践することで、他社メディアとの差別化を図り、質の高いリード獲得に繋がるコンテンツを生み出すことができます。
コツ1:製品の売り込みではなく顧客の課題解決を最優先する
BtoBの記事において最も避けるべきは、自社製品の宣伝や売り込みに終始することです。
読者は広告を見たいのではなく、自身の業務上の課題を解決するための情報を求めています。
記事の主役はあくまでも読者とその課題であり、自社製品はその解決策の一つという位置づけに留めるべきです。
まず読者の課題に深く共感を示し、その原因や背景を分析した上で、具体的な解決策を提示します。
そのプロセスの中で、自社の製品やサービスがどのように役立つのかを自然な文脈で紹介することで、読者は押し付けがましさを感じることなく、有益な情報として受け入れてくれます。
コツ2:社内の専門家の知見を借りてコンテンツの質を向上させる
記事の専門性や信頼性を高める上で、社内のリソースを最大限に活用することは非常に有効です。
マーケティング担当者だけでは持ち得ない深い専門知識や、顧客と直接接しているからこそ分かる現場のリアルな課題感を、営業担当者や開発者、カスタマーサポートなどの専門家からヒアリングします。
彼らの知見を記事に盛り込むことで、インターネットで検索すれば分かるような一般論に留まらない、独自性があり説得力の高いコンテンツが生まれます。
また、専門家に記事の監修を依頼することも、情報の正確性を担保し、コンテンツの質を向上させる上で効果的です。
コツ3:導入事例を用いて具体的な成功イメージを読者に持たせる
BtoBの意思決定者は、新たな製品やサービスを導入する際に、その効果やリスクを慎重に評価します。
その際、他社がどのように活用して成功したかという導入事例は、非常に強力な判断材料となります。
自社と同じような課題を抱えていた企業が、製品を導入することでどのような成果を得られたのかを具体的に示すことで、読者は自社に置き換えて導入後の成功イメージを描きやすくなります。
単なる機能紹介ではなく、導入前の課題、導入の決め手、導入後の変化をストーリーとして語ることで、製品の価値がよりリアルに伝わり、読者の導入意欲を高めることができます。
BtoBの記事作成で陥りがちな失敗パターンと回避策
多くの企業がBtoBの記事作成に取り組む中で、共通した失敗パターンに陥ることがあります。
成果が出ない原因は、多くの場合、戦略の欠如や実行プロセスの問題に起因します。
ここでは、代表的な3つの失敗パターンを挙げ、それぞれの原因と具体的な回避策について解説します。
これらの失敗例を事前に把握しておくことで、自社のメディア運営において同じ過ちを繰り返すリスクを減らし、より着実に成果へと繋げることが可能になります。
失敗例1:ターゲット設定が曖昧で誰の心にも響かない
リード獲得を焦るあまり、幅広い層にアプローチしようとしてターゲット設定が曖昧になってしまうケースがあります。
しかし、「すべての人」に向けたメッセージは、結局「誰の心にも深く刺さらない」当たり障りのない内容になりがちです。
読者は、自分自身の具体的な課題に言及されていない記事を「自分ごと」として捉えることができず、すぐに離脱してしまいます。
この失敗を回避するためには、記事作成のステップで解説したペルソナ設計を徹底することが不可欠です。
特定の業界の特定の役職者が抱える、ニッチで具体的な悩みに焦点を当てることで、読者の強い共感を得ることができます。
失敗例2:自社目線の内容で読者の満足度が低い
自社が伝えたいこと、つまり製品の機能や優位性をアピールすることばかりに終始してしまうのも、よくある失敗例です。
読者が求めているのは企業の宣伝ではなく、自身の課題を解決するための客観的で有益な情報です。
自社目線のコンテンツは、読者にとっては単なる売り込みとしか映らず、満足度を著しく低下させます。
これを回避するには、常に読者の視点に立ち、「読者は何に困っているのか」「この記事を読むことで読者は何を得られるのか」を自問自答しながら執筆する姿勢が必要です。
顧客の課題解決を最優先するという原則を徹底することが、読者の信頼を得るための鍵となります。
失敗例3:制作体制が整っておらず継続的な発信ができない
BtoBのコンテンツマーケティングは、一度記事を公開すればすぐに成果が出るものではなく、継続的な情報発信によって徐々に効果が現れる中長期的な施策です。
しかし、担当者が他の業務と兼任していたり、明確な制作フローや役割分担がなかったりすると、記事の更新が滞りがちになります。
散発的な更新では、検索エンジンからの評価も上がりにくく、読者の期待を裏切ることにもなります。
この問題を回避するためには、現実的な公開頻度や記事の制作スケジュールを事前に計画し、編集・執筆・校正といった各工程の担当者を明確にした運用体制を構築することが重要です。
記事作成は内製すべき?外注すべき?自社に合った体制の選び方
BtoBの記事作成を継続的に行っていく上で、「社内で制作する(内製)」か「外部の専門会社に委託する(外注)」かという体制の問題は避けて通れません。
どちらの方法にもメリット・デメリットが存在し、どちらが一方的に優れているというわけではありません。
自社の事業フェーズ、社内リソースの状況、コンテンツに求める専門性のレベルなどを総合的に考慮し、最適な体制を選択することが、施策を成功させるための重要な要素となります。
社内リソースで記事作成を進める場合のメリット
内製で記事作成を行う最大のメリットは、自社が持つ製品知識や業界への深い理解をコンテンツに直接反映できる点です。
これにより、他社には真似のできない、独自性と専門性の高い記事を作成しやすくなります。
また、営業担当者や開発者など、顧客の課題を熟知している社員と直接連携できるため、質の高い情報をスピーディーに記事化できます。
さらに、記事作成のノウハウが社内に蓄積されていくため、長期的には企業の無形資産となります。
外部に委託するコストが発生しない点も、特にリソースが限られる企業にとっては大きな利点です。
記事作成を外注(外部委託)する場合のメリット
記事作成を外注するメリットは、SEOやコンテンツ制作の専門的なスキルを持つプロフェッショナルの力を活用できることです。
これにより、社内に専門知識を持つ人材がいない場合でも、短期間で質の高い記事を安定的に量産する体制を構築できます。
社内の担当者は、記事の執筆といった実務作業から解放され、全体の戦略設計や企画、効果測定といったより上流の工程に集中することが可能です。
また、外部の客観的な視点を取り入れることで、社内では気づかなかった新たな記事の切り口やターゲットのニーズを発見できる可能性もあります。
信頼できる記事作成代行会社の選び方
記事作成の外注で成果を出すには、信頼できるパートナー選びが不可欠です。
まず確認すべきは、自社の業界やBtoBマーケティングに関する実績が豊富かどうかです。
過去にどのような企業のコンテンツを制作してきたか、具体的な事例を見せてもらうと良いでしょう。
次に、コミュニケーションが円滑に行えるかも重要なポイントです。
自社の事業や目的を深く理解し、意図を正確に汲み取ってくれる担当者がいるかを確認します。
さらに、記事の品質を担保するための編集・校正体制が整っているか、料金体系が明確で分かりやすいかといった点も、契約前に必ずチェックすべき項目です。
まとめ
BtoBビジネスにおけるリード獲得を目的とした記事作成は、BtoCとの購買プロセスの違いを深く理解することから始まります。
成果に繋げるためには、事業目標から逆算したKPI設定、具体的なペルソナ設計、顧客課題に基づくキーワード選定、検索意図を満たす構成作成、専門性の高い執筆、CTAの設置、そして公開後の分析・改善という一貫した戦略的プロセスが不可欠です。
顧客の課題解決を最優先し、社内の専門知識や導入事例を活用してコンテンツの質を高めることが、読者からの信頼獲得に繋がります。
自社のリソースや状況に応じて内製と外注を適切に選択し、継続的な情報発信体制を構築することが重要です。