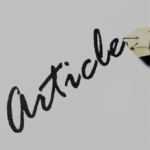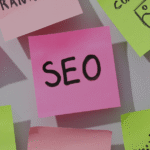Webサイトの集客において、テキストコンテンツだけでなく画像や動画を活用したSEO対策の重要性が増しています。
検索結果画面(SERP)では、通常のWebページに加えて画像や動画が表示される機会が増えており、これらを最適化することで新たな流入経路の確保が期待できます。
この記事では、画像・動画SEOが重要視される理由から、SERPで上位表示を目指すための具体的な7つの方法、さらに施策の効果を測定する手法までを解説します。
画像・動画SEOが重要視される理由とSERPでの表示形式
近年、検索エンジンの進化に伴い、画像や動画コンテンツのSEOにおける価値が高まっています。
これは、Googleが導入したユニバーサル検索によって、Webページだけでなく様々な形式のコンテンツが検索結果に統合して表示されるようになったためです。
ユーザーにとっても、テキストだけでは伝わりにくい情報を視覚的に補う画像や動画は、コンテンツの理解を助ける重要な要素です。
こうした背景から、画像・動画の最適化はサイト全体の評価を高める上で不可欠な施策となっています。
ユニバーサル検索で増える画像・動画の露出機会
ユニバーサル検索とは、Webページの検索結果に画像、動画、ニュース、地図といった多様なコンテンツを統合して表示する仕組みです。
この導入により、ユーザーは一つの検索キーワードで様々な形式の情報にアクセスできるようになりました。
Webサイト運営者にとっては、作成した画像や動画が通常の検索結果ページの上位に表示されるチャンスが生まれたことを意味します。
例えば、料理のレシピを検索した際に、作り方の手順を解説した動画や完成写真がテキスト記事と並んで表示されることがあります。
このように、画像や動画コンテンツを適切に最適化すれば、独立した流入経路として機能し、サイトへのトラフィック増加に貢献します。
視覚的な情報がユーザーの理解を深める
テキスト情報だけでは伝えきれない複雑な内容や専門的な知識も、画像や動画を用いることで直感的に分かりやすく伝えられます。
例えば、製品の使い方やサービスの仕組みを説明する際に、図解や実際の操作動画を挿入すれば、ユーザーはよりスムーズに内容を理解できるでしょう。
視覚的な情報はユーザーの理解度を高め、コンテンツへの満足度を向上させる効果があります。
その結果、ページの滞在時間が延びたり、離脱率が低下したりといったエンゲージメントの改善につながります。
こうしたユーザー行動の指標は検索エンジンにも評価されるため、間接的にWebサイト全体のSEO評価を高める要因となります。
SERP上位表示を目指す!画像・動画SEOの具体的な7つの方法
画像や動画を検索結果の上位に表示させるためには、検索エンジンがその内容を正しく理解できるよう手助けをする必要があります。
ここからは、具体的な画像最適化の施策として、ファイル名の設定やalt属性の記述といった基本的な対策から、ページの表示速度に影響するファイルサイズの圧縮、次世代フォーマット「WebP」の活用、さらには構造化データの実装まで、明日から実践できる7つの方法を具体的に解説していきます。
【方法1】検索キーワードを含んだファイル名に設定する
画像や動画をアップロードする際、ファイル名を初期設定のままにせず、コンテンツの内容と関連性の高いものに変更することが重要です。
例えば、「DSC00123.jpg」のような無意味な文字列ではなく、「seo-ranking-method.jpg」のように、検索キーワードをハイフンでつないだ具体的なファイル名に設定します。
これにより、検索エンジンはファイル名を手がかりに、その画像が何についてのものかをより正確に理解できるようになります。
ファイル名は、ユーザーが検索するであろうキーワードを意識して、簡潔かつ具体的に記述することがポイントです。
この一手間が、画像検索結果での上位表示につながる第一歩となります。
【方法2】alt属性(代替テキスト)に画像の内容を正確に記述する
alt属性(代替テキスト)は、通信環境の問題などで画像が表示されなかった場合に、画像の代わりに表示されるテキストです。
また、スクリーンリーダーなどの音声読み上げソフトが画像の内容を説明するためにも利用され、Webアクセシビリティの観点からも非常に重要です。
SEOにおいては、検索エンジンが画像の内容を理解するための重要な手がかりとなります。
alt属性には、画像が何を表しているのかを具体的かつ簡潔に記述し、関連するキーワードを自然な形で含めることが求められます。
単なるキーワードの羅列ではなく、文脈に沿った分かりやすいテキストを設定することで、画像検索での評価を高められます。
【方法3】ページの表示速度を上げるためファイルサイズを圧縮する
Webページに掲載する画像のファイルサイズは、ページの表示速度に直接影響を与えます。
ファイルサイズが大きすぎるとページの読み込みが遅くなり、ユーザーはストレスを感じて離脱する可能性が高まります。
ページの表示速度はGoogleのランキング要因の一つでもあるため、画像の軽量化は必須の対策です。
専用の圧縮ツールや画像編集ソフト、WordPressのプラグインなどを使えば、画質を大きく損なうことなく画像サイズを削減できます。
ユーザー体験の向上とSEO評価の維持のためにも、Webサイトにアップロードする画像は必ず圧縮し、ファイルサイズを最適化する習慣をつけましょう。
【方法4】次世代フォーマット「WebP」で画質を保ちつつ軽量化する
WebPは、Googleが開発した次世代画像フォーマットです。
JPEGやPNGといった従来のフォーマットと比較して圧縮率が非常に高く、同程度の画質を維持しながらファイルサイズを大幅に削減できるという大きなメリットがあります。
画像のファイルサイズが小さくなることで、Webページの表示速度が向上し、ユーザー体験の改善とSEO評価の向上に直接的に貢献します。
多くのモダンブラウザがWebPに対応しており、導入のハードルは低くなっています。
特にWordPressを利用している場合、専用のプラグインを導入するだけで既存の画像を簡単にWebPへ変換・配信することが可能です。
【方法5】動画のタイトル・説明文にキーワードを盛り込む
動画コンテンツを検索結果で上位表示させるためには、動画の内容を検索エンジンとユーザーに的確に伝える情報設定が不可欠です。
まず、動画のタイトルには、ユーザーが検索するであろう最も重要なキーワードを含め、内容が一目でわかるように工夫します。
説明文には、タイトルで伝えきれなかった動画の概要や補足情報を記述し、関連キーワードを自然な形で複数盛り込みます。
これにより、検索エンジンは動画のテーマをより深く理解できます。
また、検索結果に表示されるサムネイルはクリック率を大きく左右するため、動画の魅力を凝縮した、ユーザーの興味を引くデザインにすることが求められます。
【方法6】構造化データをマークアップしてリッチリザルトを狙う
構造化データとは、HTMLに特定の記述を追加することで、Webページの内容を検索エンジンに対してより明確に伝えるためのデータ形式です。
画像や動画に対して構造化データを正しく設定すると、検索結果画面で通常よりも多くの情報が表示される「リッチリザルト」としての表示が期待できます。
例えば、動画の場合、サムネイル画像やアップロード日、再生時間などが検索結果に表示されることがあります。
こうした付加情報は検索結果の中でコンテンツを目立たせ、ユーザーのクリックを促す効果があります。
レシピサイトの調理時間やレビューサイトの評価点など、コンテンツの種類に応じたスキーマを選択して実装することが重要です。
【方法7】サイトマップでGoogleに画像・動画の存在を伝える
サイトマップ(XMLサイトマップ)は、Webサイト内にどのようなページが存在するかを検索エンジンに伝えるためのファイルです。
通常のサイトマップに加えて、画像や動画に特化した情報を記載したサイトマップを別途作成・送信することで、これらのメディアコンテンツの存在を検索エンジンに効率よく、かつ網羅的に通知できます。
特に、JavaScriptで読み込まれる画像や、サイトに追加したばかりの新しい動画コンテンツは、検索エンジンに発見されにくい場合があります。
専用のサイトマップをGoogleサーチコンソールから送信することで、クロールとインデックス登録を促進し、検索結果に表示されるまでの時間を短縮する効果が期待できます。
実施した画像・動画SEOの効果を測定する方法
画像や動画に関するSEO施策を実施した後は、その効果を正しく測定し、次の改善アクションにつなげることが極めて重要です。
施策が検索順位やサイトへの流入にどのような影響を与えたのかをデータに基づいて把握しなければ、改善は進みません。
ここでは、Googleが無料で提供している「Googleサーチコンソール」と「Googleアナリティクス」という2つのツールを用いて、施策の効果を定量的・定性的に分析する具体的な方法について解説します。
Googleサーチコンソールで検索順位とクリック率を確認する
Googleサーチコンソールは、Google検索におけるWebサイトのパフォーマンスを監視・分析できるツールです。
「検索パフォーマンス」レポートでは、サイトがどのようなキーワードで検索結果に表示されたか、その際の表示回数、クリック数、平均CTR(クリック率)、平均掲載順位といった指標を確認できます。
画像・動画SEOの効果を測定する際は、レポート上部の「検索タイプ」フィルタを「画像」または「動画」に切り替えることで、それぞれの検索結果に特化したデータを分析可能です。
施策実行の前後でこれらの数値を比較し、表示回数やクリック数が増加しているか、掲載順位が上昇しているかを確認することで、施策の効果を客観的に評価します。
Googleアナリティクスでユーザーの流入後の動きを分析する
Googleアナリティクスは、Webサイトにアクセスしたユーザーの行動を詳細に分析するためのツールです。
画像検索や動画検索経由でサイトを訪れたユーザーが、その後どのような行動をとったかを知ることで、コンテンツの質やサイトの構成が適切であったかを評価できます。
具体的には、「集客」レポートで参照元を確認し、画像検索(images.google.comなど)からの流入セッションを特定します。
そして、そのセッションにおけるページの滞在時間、直帰率、コンバージョン率などを分析します。
もし滞在時間が短く直帰率が高い場合は、コンテンツがユーザーの検索意図と合致していなかった可能性があり、コンテンツの改善が必要と判断できます。
まとめ
本記事では、画像・動画SEOが重要視される背景から、SERPで上位表示を目指すための具体的な7つの方法、そして施策の効果測定手法までを解説しました。
ユニバーサル検索の普及により、画像や動画はWebサイトへの重要な流入経路となっています。
ファイル名の設定やalt属性の記述といった基本的な最適化から、WebPの活用による表示速度改善、構造化データによるリッチリザルトの獲得、サイトマップによるインデックス促進まで、多角的なアプローチが求められます。
施策実行後は、Googleサーチコンソールやアナリティクスを用いて効果を検証し、継続的な改善サイクルを回していくことが、競争の激しい検索市場で成果を出すための鍵となります。